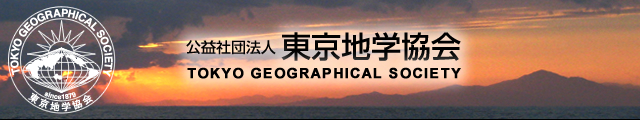公益社団法人 東京地学協会
会 長 田林 明
東京地学協会は1879(明治12)年に、当時の日本の社会へ外国の諸事情を紹介することを意図して創立されました。その頃のヨーロッパ諸国の都市にあった地理学協会、特にロンドンの王立地理学協会を参考にしたと言われています。初期の会員は皇族や華族、政治家や外交官、軍人などでしたが、日本で地学が発展するにつれて、その専門家が中心になって協会の運営を担うようになりました。当初は探検記や外国事情を掲載する東京地学協会報告を発行していましたが、帝国大学の地質学者たちがつくる地学会と合併して、1893(明治26)年から地学雑誌が本協会から刊行されることになりました。それ以来地学のすべての分野を対象とする学術雑誌として現在に至っています。ここで言う地学は地質鉱物学、人文地理学を含む地理学、地球物理学、地球化学など地球に関わる多様な分野を含んでおり、これらの専門分野それぞれを深めるとともに分野相互の連携をはかり、地学の総合的な発展を推進することが本協会の重要な目的となっています。
近年では地球温暖化や大気汚染、海洋の酸性化などの地球規模の環境変化から局地的な環境異変にいたる様々な自然変化、地震や津波、火山噴火、豪雨、洪水といった自然災害、水資源や地下資源、エネルーギー資源など、地学にかかわる現象に対する社会の関心が高まっています。地圏と水圏と気圏とともに、それらから生まれた多様な生態系とそれを利用して生活してきた人間の活動も地学の対象となります。人口の過密と過疎、少子化と高齢化、都市や地域の問題、さらには近年の国家間の対立や異なった文化や民族の衝突などへの取り組みも地学に含まれます。広く総合的に「地」を「学ぶ」ことから、適切な方策を探るといった本協会の活動が大きな役割をもっています。
ところが日本の学校教育のなかでは地学や地理学は重視されておらず、「地」を学び理解し、重要な「地」の原理を発見し、それを次の世代に伝えていくことが必ずしも順調に行われていません。そのため地学現象の重要性にもかかわらず、一般社会の地学への関心はなかなか高まりません。このような状況の改善もしていかねばなりません。
本協会は機関誌「地学雑誌」を年間6冊発行し、特定の分野に特化した地学の専門的な知見のみならず、広い範囲を念頭においた学際的な成果の発信に努めています。また学術講演会、見学会、談話会などを開催しています。さらに設立当初からかかわってきた国際的な活動を推進してきており、その一環として国際地理学会議の共催や国際地理・地学オリンピックの後援・助成を行ってきました。各種の助成事業として、調査・研究、国際的研究集会、地学に関わる出版、地学・地理クラブ活動および地学・地理教育等などに対する助成があります。本協会は関連する専門分野の学会と協力しながら、地学の発展と普及に務めていきます。そのために地学に関する公益事業を充実させたいと考えていますので、皆様方のご協力をお願いいたします。
田林新会長からのあいさつにつきましては、現在準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。